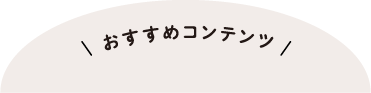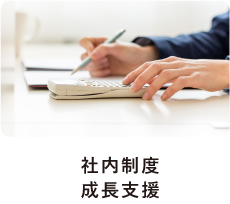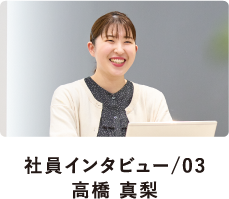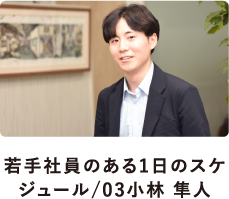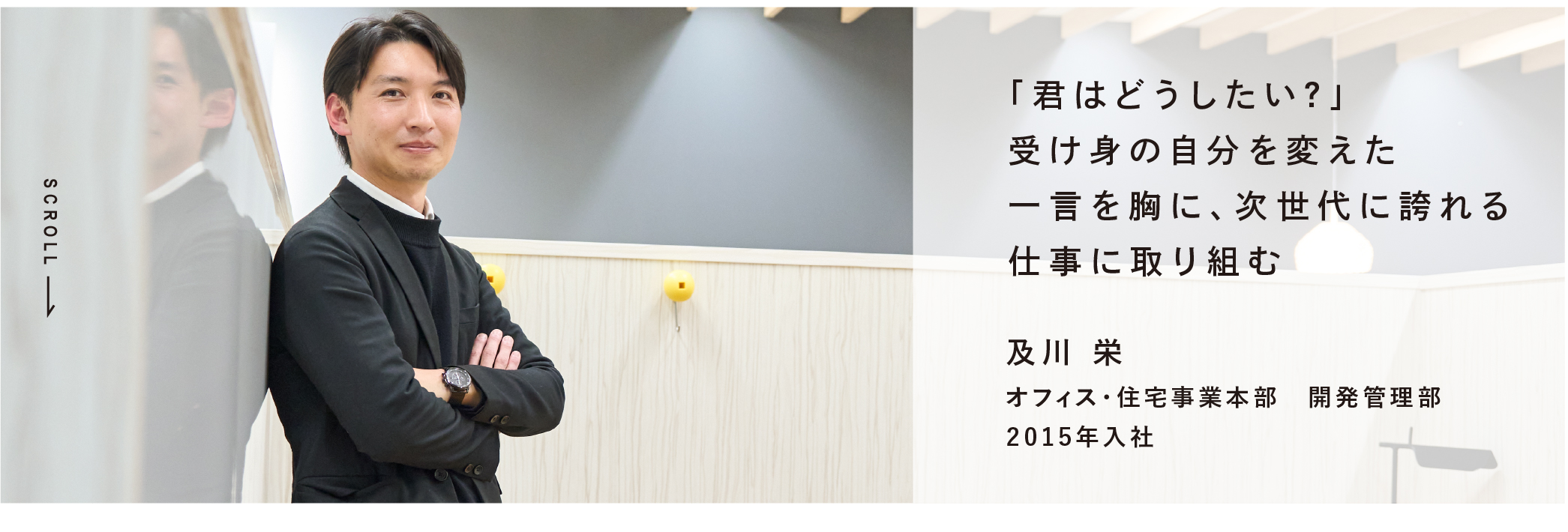
社内最大規模のプロジェクトに自ら志願
苦労もあるけどやりがいのある日々
2015年に入社し、現在は本社のオフィス・住宅事業本部に所属しています。担当業務としては、入社5年目のときに社内で公募があり、立候補して参画した「(仮称)船橋市場町プロジェクト」という大規模複合住宅開発に携わっています。本プロジェクトの目指す姿は、4.5ヘクタールという広大な土地で、商業施設、賃貸住宅、分譲住宅の大きく3つの要素からなる複合型街づくりです。その中で私は賃貸住宅企画をメインとして担いつつ、今回計画は、部署も横断してのプロジェクトとなることから、各箇所と調整を行う橋渡し的な役割も併せて担っています。また本計画では、道路や公園の開発の他、開発協議や地区計画協議などJRと協力しての行政とのやり取りや、パートナーである東急不動産様と連携で行うエリアマネジメント、エネルギーマネジメントなど、全体に関わる事柄もあり、社外の方との折衝や調整なども重要です。ただでさえ住宅開発事業に関わるのが初めてなことに加え、多くの関係者が関わる計画だったので、最初はかなり苦労しました。それでも自分から手を挙げたことなので、できることを地道に積み重ねて今に至っています。

受け身な自分を変えてくれた
「君はどうしたい?」という言葉
入社から3年ほどは支社で物件の開発や管理などをしていました。
最初は高架下施設の開発業務だけを担当していたのですが、途中から所属箇所再編に伴って、管理も請け負うことになり、そのときにテナント様と直接やりとりなど、当社の基幹事業の基本を学びました。さらに、社会人として今でも私自身の指針としている大切な言葉をはじめて上司や先輩からもらったのもこの時期です。私はもともと保守的で受け身なタイプで、自分から意見を主張するのではなく、全体が円滑に進むように自身の意思を抑えて立ち回る傾向がありました。そんな自分に当時の上司、先輩から幾度となく言われたのが「君はどうしたい?」という言葉です。デベロッパーの主たる仕事は「考える」こと、そして、設計士やコンサルからの提案を参考に物事を「決める」ことであると個人的に考えています。そのためには常に自分の理想ややりたいことを、言語化するように心がけることが大切です。そういった背景から「君はどうしたい?」という言葉を戒めに、受け身でなく主体的に自身の意見を言える様、日々努めるようにしています。性格というのは簡単に変えられるものでもないですが、意識し続けることで、徐々に自分を変えることができていると感じています。

社内コンペ「燈台」への参加が
大きな転換点に
チャレンジする意識が芽生えた
入社4年目に本社に異動し、事業推進部に配属されました。主に商業テナント様のリーシング情報の管理をしたり、新サービスの紹介・推進などを担当していましたが、それと同時に「燈台」という社内コンペにサポーターとして参加したことが、自分にとって大きな転換点となりました。それまでは既にできあがった枠組みの中で仕事をしていたのですが、「燈台」では、ゼロから事業のスキームを考えたりニーズを調査したりなど、すべて自分たちで挑戦していかなければなりません。また当時「燈台」には、外部のコンサルタントさんが関わっており、社内とは違う考え方や視点を示してくれました。そういった経験や新たな視点に触れることで、「挑戦しなければ、やりたいことは実現できない」という気づきがあり「ならばチャンスがあったら何でもやってみよう」という意識の転換が起きたのです。それが大きな刺激となり、船橋のプロジェクトにチャレンジすることにつながりました。
くじけそうな自分を突き動かすのは、
ぶれない信念と野望
「(仮称)船橋市場町プロジェクト」に携わって4年。しかし完成はまだ数年先という長期戦です。
様々なタスクをクリアしながらも、ゴールはまだずっと先。
そんな日々のなかで、モチベーションを保つには、根底となる信念や理想が必要です。
私の場合は自分の子どもだけでなく、社会全体に対して「これ、私がつくったんです」と胸を張って言いたいという理想…というよりも野望が、自身を突き動かしてくれています。このプロジェクトに限らず、デベロッパーという仕事は忍耐が必要な仕事です。私もプロジェクトに参画した当初は思うようにいかず、自信を失いかけたこともありました。しかし「次世代に誇れる仕事をしたい」という信念を胸にできることを積み重ねてきた結果、今でもプロジェクトのメンバーとして業務にあたれているのだと思います。
若手の意見が重視される風通しの良い社風
若手ならではの感性を評価してくれる
燈台のくだりでもあったように、当社はチャレンジする若手を応援してくれる企業です。
「燈台」以外にも「マイチャレンジ研修」というのがあり、事業計画の達成に向けて成長につながるような研修を自分で探して申請し、認められると受講できる制度があります。私も現在の業務に役立ちそうな、例えばエリアマネジメント講習などを見つけて受けたいと考えています。
また、社全体で若手の意見が重視されているところも良いところだと感じます。「若手の意見も聞く」ではなく、若手ならではの感性や表現力、トレンドに対する知識などを評価してくれるので意見が言いやすく、それが風通しの良さに繋がっているのではないでしょうか。
私もだんだん年齢があがってきましたが、この社風はしっかり引き継ぎ、若手のチャレンジを応援していきたいと思います。